今年の2月、上院最年長のダイアン・ファインスタイン議員(民主党:カリフォルニア州)の地元事務所に子どもの一団が押しかける事件が起きた。「何しに来たの?」と問いかける85歳の議員に対して10代前半とおぼしき子どもが放ったのは次の一言だった。「先生、Green New Dealに賛成投票してください」。Green New Dealは現実的でなく対案を準備していると説明する議員に対し、「あなたは議員として我々に選ばれたのだから、我々の言うことを聞くべきだ」と反論する子どもたち。年齢を聞かれて16歳と答える女の子の横から別の子どもが「投票権なんて関係ない。環境で影響を受けるのは我々だ」と食い下がる。この子どもを動員した抗議活動を行ったのはミレニアル世代の若者が立ち上げた環境活動家団体Sunrise Movementだ。彼らが支援推進するのが、今回テーマとしたGreen New Deal(GND)である。
ポトマック河畔より#29 | "非現実的"な環境政策では片付けられないGreen New Deal
これは、丸紅グループ広報誌『M-SPIRIT』(2019年7月発行)のコラムとして2019年5月に執筆されたものです。
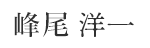

注目されるGNDと内包する課題
GNDとは何か。言葉自体は10年以上前から存在しているが、注目されるようになったのは昨年の中間選挙で初当選したアレクサンドリア・オカシオコルテス下院議員がエド・マーキー上院議員と共にGNDの決議案を提出した今年2月だ。この決議案には今後10年間で温室効果ガスの排出をネットゼロにすることに加えて、高賃金の雇用確保、インフラや産業投資、全ての国民への良質な空気・水・食品などの確保、差別の撤廃などの目標が含まれる。決議案と共にオカシオコルテス議員のWEBで開示(後に削除)されたFAQでは、原発廃止や勤労意欲の無い者も含めた最低所得保障にも言及している。新人下院議員が中心となって提案された野心的な決議案だが、多くの2020年民主党大統領候補を含む上院議員12名、下院議員90名が共同提案者に名を連ねることになった。
GNDの最大の問題はインフラ投資や社会保障にかかるコストである。GND決議案は具体的な政策は含まず正確な試算は困難だが、保守系団体のAmerican Action Forumは10年間で93兆ドル、Bloombergは年間6.6兆ドルと推定している。現在の米国GDP20兆ドルの3~4割というところか。(前述のFAQは「第二次大戦中米国はGDPの40~50%の公共投資を行い中間層の創出に寄与した」としている)。いずれにしても小さい金額では収まらないだろう。これ以外にも、労働組合の一部からの反対、風力・太陽光発電投資を巡る州ごとの合意形成の難しさ、連邦政府による膨大な投資という巨額利権にまつわる問題(政治家の地元利益誘導など)、仕組みづくりなどにかかる追加の時間やコストの問題が考えられる。
GNDと第二次世界大戦

実現性が未知数のGND決議案に多くの有力民主党議員が賛同している背景は幾つか考えられる。まず今のアメリカの景気が良いことだ。今年第1四半期のGDP成長率は3.2%。失業率は完全雇用水準の3.6%である。誰もが職を持ち、前年比較で若干でも豊かになっている状況下、目先の雇用確保や景気てこ入れなどの現実的な政策への注目度は低い。むしろ所得格差や教育費・医療費高騰への不満・閉塞感を一気に解消するGNDのような大きなアイデアの方が受けが良い。次に民主党の2020年の議会・大統領選挙対策だ。2016年の選挙でトランプ候補はアメリカンドリームを奪った中国・メキシコをはじめとする「敵」を作り、その敵からアメリカを「守る」という概念で多くの賛同者を得た。立候補時には泡沫候補の一人だったトランプを大統領の座に押し上げた一因である。今回それに対抗して「敵」を作らねばならない民主党にとって、骨太で分かりやすくビジュアルに訴えやすい気候変動はうってつけだった。トランプ大統領が人為的な気候温暖化に懐疑的であったことも大きいだろう。さらに注目すべきは冒頭にもあった「環境破壊の影響を受けるのは子どもたち」という概念だ。ミレニアル世代が有権者の3割を占めるに至った今、環境破壊の元凶である化石燃料の利権で肥え太る年寄りたちを敵として攻撃し、若者の票を集めるというのは政治的に正しいやり方だ。また気候変動対応に財政出動で巨額の投資を行い高賃金の仕事を確保するというのは組合労働者の票を獲得する意図だろう。都会の高学歴層・LGBTQ・有色人種・組合労働者の寄せ集めを支持層とする民主党は、2016年選挙でトランプにこの組合労働者を奪われた。気候変動対応だけでは彼らの票を取り戻すことは難しい。そこにGNDがGreen以外の要素を含む背景がある。
GND決議案では2カ所、FAQでは4カ所で「第二次世界大戦」という言葉が使われている。日本という「卑怯で凶暴な」共通の敵を得たことでこの国は1つになれた。その70年以上前の経験則が21世紀の今日、再び持ち出されるところに、多様化が進んだ今のアメリカで票を獲得することの難しさやGND推進者たちの真剣さがうかがえる。GNDが単に野心的で非現実的な環境対策決議案では片付けられないことは明らかだ。
他の記事について
-

-

-
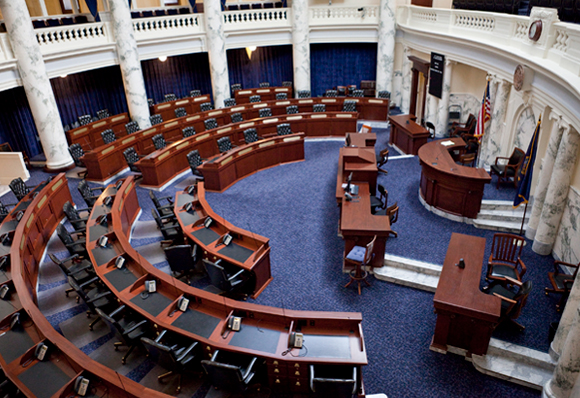
-

-

-

-
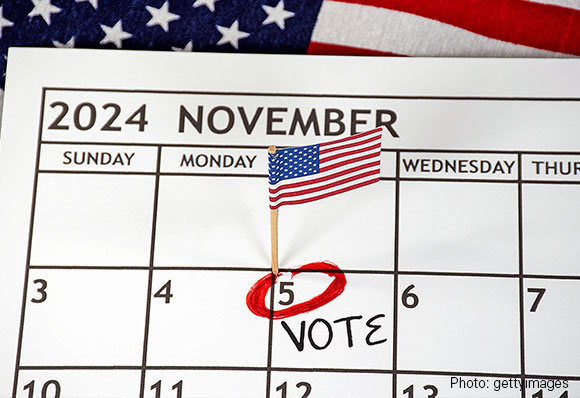
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
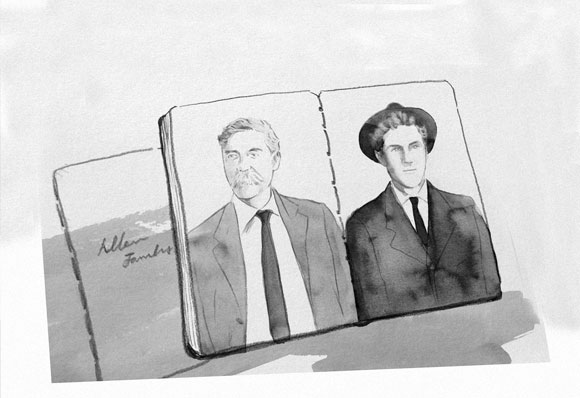
-
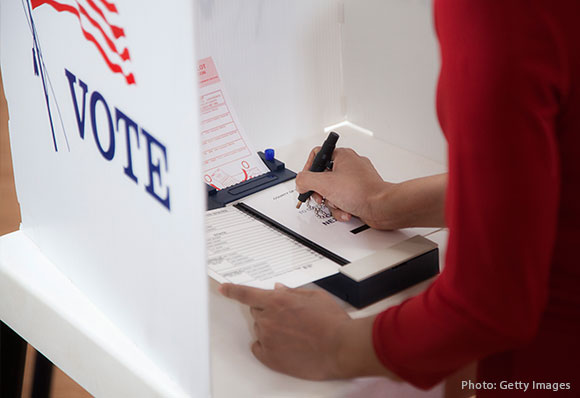
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

