今回は「米国における日本企業のプレゼンスの低下」といったよく聞く論調に対して、真っ向から反論してみたい。確かにエレクトロニクスや携帯電話など、日本企業が韓国や中国など他のアジア企業との米国市場での競争に敗れたといえる事例は少なくない。マクロで見ても、米国の輸入額に占める日本のシェアは、約20年前の1994年の18%、カナダに次ぐ2位から最近は6%前後、4位に落ち込み、中国が約19%で首位に躍進している。しかし、米国を象徴する自動車市場では日本企業のシェアが大きな割合を維持しているし、日系金融機関も金融危機のダメージを最小に抑えて米国の金融市場で復活してきているし、丸紅を含めた商社も米国で活発な投資を行って大きな収益を上げ続けている。少なくとも米国にいる筆者の実感からは、「日本企業のプレゼンスの低下」に相当の違和感を持ってしまう。
ポトマック河畔より#10 | 第二のブームを迎えている日本企業の対米国投資
新年明けましておめでとうございます。今年も丸紅グループにとって重要な市場である米国の首都ワシントンから、注目すべき問題や動きをお伝えしていきます。
これは、丸紅グループ広報誌『M-SPIRIT』(2015年1月発行)のコラムとして2014年12月に執筆されたものです。

過去最高になっている日本の対米直接投資

筆者の違和感を裏付ける統計もある。近年大幅に増えている日本から米国への直接投資である。商務省によれば、2013年は米国の日本からの直接投資額は449億ドルに達し、国別では1992年以来21年ぶりに最大になった。日本企業のプレゼンスの低下という場合に比較されがちな国は中国と韓国だが、両国からの同投資額は少なく、中国が日本の3%、韓国は15%でしかない。しかも最新の直接投資残高で比較すれば、その差はさらに広がる。米国における各国企業のプレゼンスを比較するのなら、米国で各企業が創出する雇用や付加価値の規模を比べるべきであり、その指標として直接投資が輸入や特定の業種や商品のシェアよりも適していることは論をまたない。その直接投資でみれば、日本のプレゼンスは最近、むしろ高まっているのである。
しかし、この事実が日米のメディアでも市場でもあまり理解されていない。その背景には、日本経済の「失われた20年」の長期停滞がもたらした日本企業に対する無関心の定着がある。日本の直接投資の増加がこの程度では、関心は高まらない。もう一つは、その「失われた20年」の前の日本のバブル期にあたる1988年から1990年にかけて生じた日本企業の対米投資ブームの影響である。この時期の日本からの直接投資は年間180億ドル前後に達したが、その後に多額の損失を発生させて撤退する事例が多く、投資自体も2000年代半ばまで長い低迷が続いた。この極端な失速を日米のメディアも市場もまったく予測できず、逆にブームの渦中では米国を象徴する企業が初めて日本企業の買収対象になった驚きも影響して、「凋落する米国、台頭する日本」という意識が日米双方に広がり、米国では不安感、日本では過信をそれぞれ招いた。この過剰反応は踊らされた者にとっては忘れたい過去になり、今まで続く日本の経済と企業に対する無関心となって、現在の投資の大幅な増加への鈍感な反応をもたらしているのである。
米国で強さを見せ始めた日本企業という視点を持つべき

しかし現実には、バブル期を圧倒する規模と質で日本企業の第二次の対米投資ブームが生じている。2013年の米国企業が関わるクロスボーダーM&A取引額の上位ランキングを見ても、首位がソフトバンクによる米通信企業スプリント買収の216億ドル、5位が丸紅による米穀物大手ガビロン買収の27億ドルである。2014年も、サントリーによる米蒸留酒最大手ビームの買収の160億ドルが上位に入る見通しである。年間のトップ5の2件を日本企業が占めたことも、丸紅がランク入りしたことも史上初だろう。
しかもこの第二の対米投資ブームは、構造改革が進んだ日本企業の対米国戦略の転換の成果でもあり、一過性の現象に終わったバブル期のブームとは比較にならない強さを秘めているという重要な特徴がある。今、積極的に米国への投資を行っている日本企業とは、日本経済の「失われた20年」という厳しい事業環境の下でも徹底した経営改革を進めて生き残り、競争の厳しい米国市場において基盤となり収益力のある子会社を育て上げ、その上に果敢に新規投資を続けている企業である。最近の日本の多額の対米投資とは、そうした優れた日本企業の数が増えた表れでもある。
日本経済はいまだに長期停滞を脱しきれない状態が続いているが、丸紅グループを含めて、米国で積極的な活動を展開する日本企業は着実に増え、世界で最も競争が激しい米国市場において第二の投資ブームが生じるまでになっている。この事実を額面どおりに捉え、近い将来に起こる日本経済の再生の予兆と捉えてもいいのではないかと筆者は今考えている。
他の記事について
-

-

-
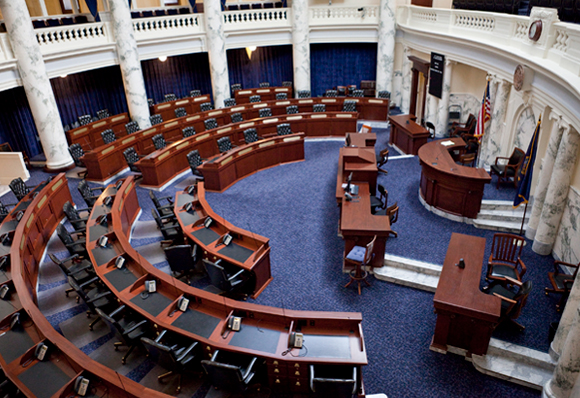
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

