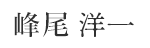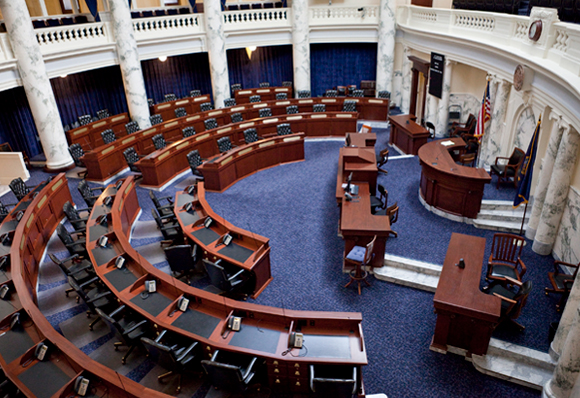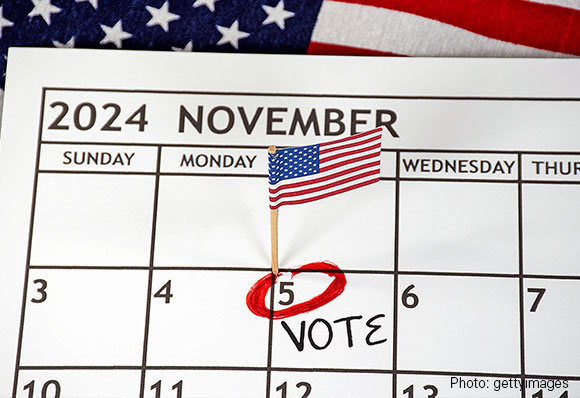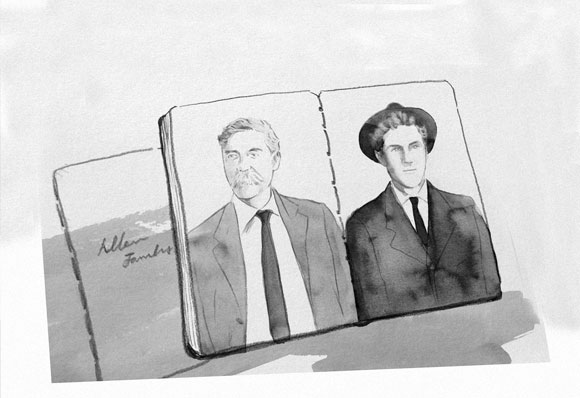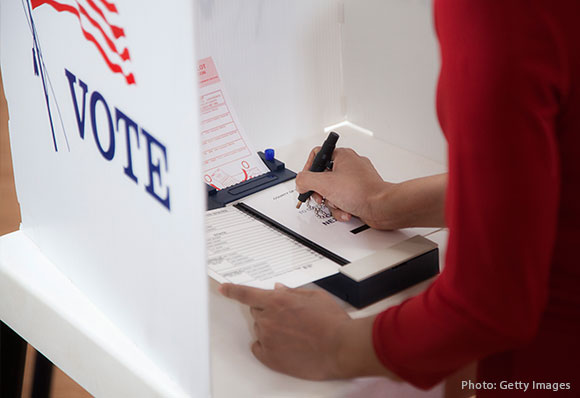アメリカの量販店に7~8月ごろに行くと必ず見掛けるのがBack to schoolという札である。筆者が20年前にアメリカに来た時にこれを見て、何を意味するのか理解に苦しんだ記憶がある。単純に意味を言えば、新学期セールコーナー、といったところであろうか。もちろんそうした概念や売り場は日本にもあるし、小学校に上がるときにランドセルを買う、中学生になるときに制服を買う、新学期で新たな文房具を買う、という慣習も普通に存在する。だが、規模や内容、特定の買い物が習慣として定着している点で異なる部分も多い。
まず規模でいうと、アメリカでは2021年の推計で一家計当たり849ドル(総額で371億ドル)を学用品に消費している。日本にBack to school shoppingのみの数字は見つからないが、毎年新学期に平均849ドル(1ドル110円として9万3390円)が拠出されるというのは想像し難い。この規模感がアメリカに於いてBack to school shoppingの概念が定着している背景だろう。この849ドルの内の4割弱は洋服やカバンである。日本の小学校のようにランドセルを卒業まで使う習慣はなく、新学期が始まるたびにバックパックや靴、洋服を買うのが普通である。