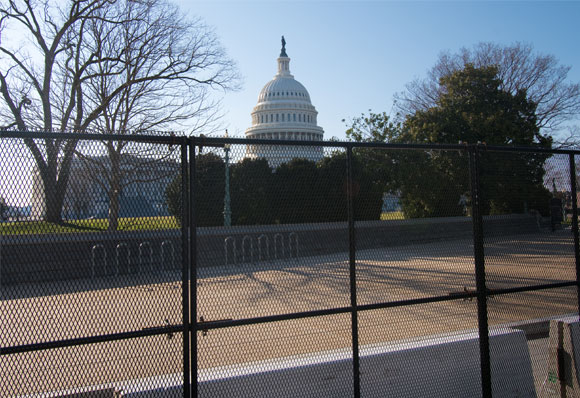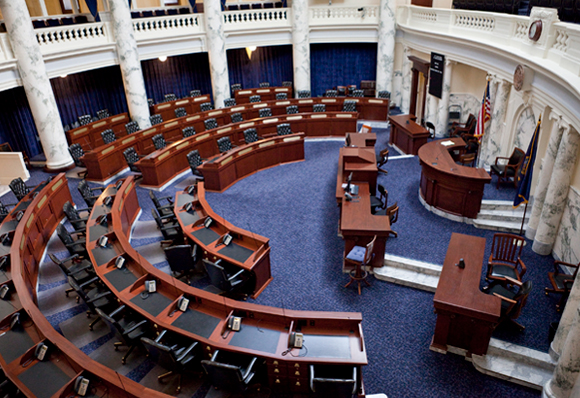高すぎる学費。現在の米国の大学教育への批判は、この点に集中している。実際、授業料(諸経費含む)は過去20年間で3倍に膨らんだ。この間に約1.5倍になった消費者物価と比べても著しい上昇率である。実際、今年の4年制大学の授業料は私立で年間平均3万1000ドル、その中でも有名大学は特に高く、最高のコロンビア大学は5万1000ドルである。州立大学は同平均9000ドル強と私立よりも割安だが、授業料の最近の上昇率は州財政の悪化のため、私立を上回っている。しかも、私立も公立も、授業料に加えて年間で合計1万ドルを超える居住費等の負担が必要になる。
この膨らんだ学費の支払いは、学生にとって重い負担になっている。米国では平均すれば学費の3割は奨学金で賄われ、4割は親や親類が負担しているが、残り3割は学生個人の負担である。それはアルバイトで賄える金額ではなく、学生の約7割が学生ローンを利用しているという。卒業時に抱える負債額も少なくなく、2013年に大学を卒業した学生で平均2万8000ドル、国全体のローン残高も2014年9月末時点で1兆1000億ドルに達しているという。その返済の大変さは、景気回復の進展とともに住宅や自動車など大半のローンの延滞率が低下傾向にあるのに、学生ローンだけは延滞率が11%前後に高止まりして、各種ローンの中で最高になっていることからも分かる。
しかし、これだけ学費とローンの負担が膨れ上がり社会問題になっても、労働経済学の観点からは、米国において大学に行く価値は余りあるほど大きいという。その証拠が、大卒・高卒間の賃金格差が圧倒的に大きく、その拡大が止まらないことである。同格差は80年代初期には64%だったが、それ以降は上昇が続き2013年には98%に達した。しかも生涯所得では大卒者が高卒者を平均80万ドル上回るから、将来の所得が現在の所得より価値が低いことなどを勘案しても、3万ドル近い学生ローンなら将来への投資としては平均的にみて十分割に合うのである。オバマ大統領も、最近の演説の中で、「大学の学位はミドルクラスへの最も確実なチケットである」と述べている。