しかも、米国政府はこの子供たちの大半をすぐには強制送還できない。約4分の3は中米のホンジュラス、エルサルバドル、グアテマラの出身であり、米国政府は「2008年人身取引被害者保護再授権法」によって、この子供たちが人身売買の被害者でないか、審査を義務付けられている。実際に被害者と認定されて米国での滞在を許される子供は限られる模様だが、審査を担当する移民裁判所には9万人の審査を短期間で行う対応能力などない。このままでは、数万人の子供が長い間、米国内で評決まで待機させられる異常事態が避けられないとの見方が多い。
ポトマック河畔より#08 | 「国境と人道の危機」に直面する米国
米国が新たな危機に直面している。最近数カ月で、メキシコとの国境から家族の同伴なく不法入国して身柄を拘束される子供が急増するという「国境と人道の危機」が生じているのだ。国土安全保障省は、2014年度(昨年10月から今年9月末)のその人数が9万人、前年度の2.3倍に膨らむとみている。
これは、丸紅グループ広報誌『M-SPIRIT』(2014年9月発行)のコラムとして2014年8月に執筆されたものです。
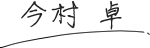
原因の多くは中米各国にあるが


密入国する子供が増えた最大の理由は、中米3カ国の深刻な暴力と貧困である。2012年の人口10万人あたりの殺人発生率はホンジュラスが90件で世界最悪、エルサルバドルとグアテマラの件数はその半分だが順位は4位と5位である。これらの国々の親たちは、子供だけでアメリカまで行かせる危険は承知の上で「母国にとどめておくよりもまし」と恐怖に駆られているのだ。米国政府の審査基準では、3カ国のうちエルサルバドルやグアテマラの治安はそこまで悪くはないが、中米の犯罪組織や子供達の密入国を斡旋する請負業者に関する過激な情報が親の不安を煽っている。
しかも、子供を送り出す親の間には、「今、アメリカに行けば市民権が与えられる」「強制送還などされない」といった嘘も広がっている。オバマ政権は不法移民の市民権獲得に道を開く政策を追求しているが、対象は幼い頃に親につれて来られて米国で育った不法移民である。大統領も「今から米国に不法入国する子供に市民権が与えられる可能性はない」と明言している。だが、中米3カ国の政府は正しい情報を伝える力を欠き、親には犯罪組織が流布する誤った情報しか届かない。
また、米国に滞在する中米3カ国の親が、現在の米国の制度とルールを逆手にとって母国に残した子供を呼び寄せている例も少なくない。「2008年人身取引被害者保護再授権法」により、密入国して拘束された子供は、米国に親がいれば移民裁判所の評決まで親元で保護される。しかも評決まで一緒に暮らせる期間は長いのだ。実際、エルサルバドルからの移民が多いワシントン近郊のメリーランドとバージニアの2州では、親に保護された密入国の子供が合計で4500人近くもいる。
打開策は見出せず、政権にも米国にもダメージ

オバマ政権は、この「国境と人道の危機」への打開策を見出せていない。大統領は議会に子供の審査の迅速化など緊急追加予算を求めたが、議会は多数派が共和党の下院と、民主党の上院の調整が進まないまま、夏休みに入ってしまった。特に共和党は党内の保守強硬派の発言力が増し、中米3カ国の子供をすぐに強制送還できるように「2008年人身取引被害者保護再授権法」の改正を求めるだけでなく、2012年にオバマ大統領が署名した若年不法移民の救済策を定めた大統領令の撤回まで迫る強硬姿勢である。この党派対立から妥協案がまとまるとは到底思えない。
今言えることは、周辺諸国との経済や治安の圧倒的な格差がある米国が、安定した移民制度を維持することの難しさであろう。共和党は現政権の移民規制緩和を非難するが、オバマ政権下で強制送還された不法移民の数はブッシュ前政権より多く200万人超である。民主党内の左派や中南米系移民の支援団体はオバマ大統領を「最多国外追放長官」と批判しているほどであり、オバマ政権が過度に移民規制を緩和しているわけではない。むしろ、中米諸国で治安の悪化する国が増えて、そこから米国への人の流入増加への圧力が強まってしまっているという情勢に対し、米国の社会の安定を維持するために移民制度に関してイデオロギーにとらわれず必要な措置を講じていると評価すべきだろう。それでも、今回の国境・人道危機は防げなかったし、その打開策も見出せず混乱が続くために、年内の包括的な移民制度改革の前進は困難になってしまった。そうした意味でも、今回の危機がオバマ政権と米国の経済と社会に与えるダメージは大きいと考えざるを得ないのかもしれない。
他の記事について
-

-

-
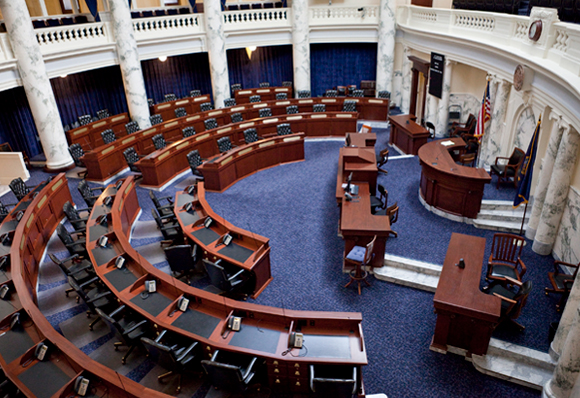
-

-

-

-
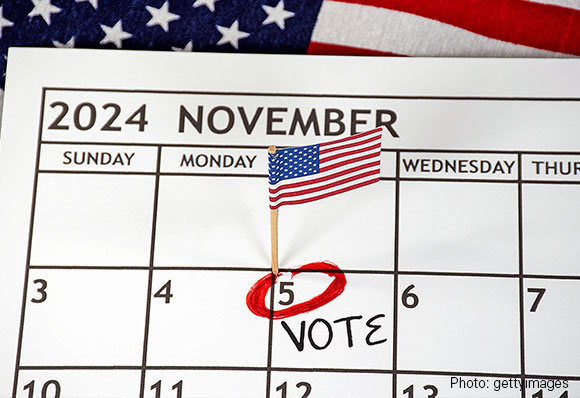
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
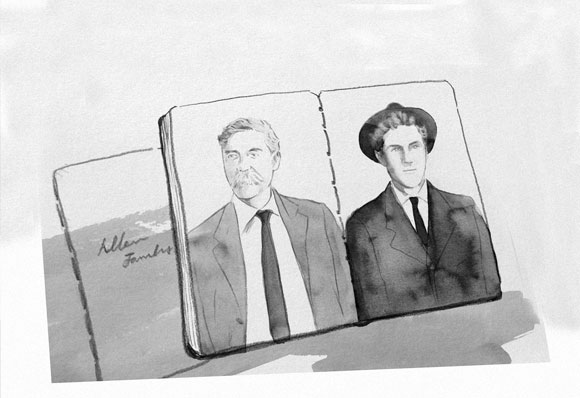
-
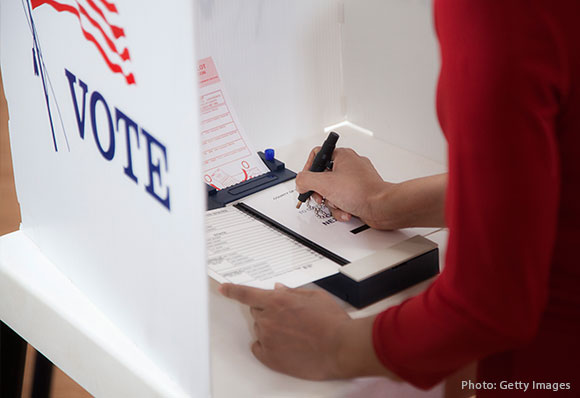
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

