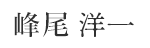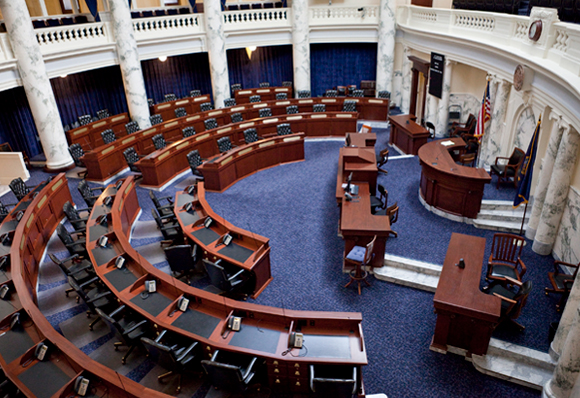マーシャル諸島・ミクロネシア・ナウル・パラオ・パプアニューギニア・スリナム・トンガ・アメリカ合衆国。この8カ国には共通項がある。有給の産休制度を持たないことだ。世界最大のGDPを誇り、人権にも関心が高いアメリカ。何故ここまで子育てに“非協力的”なのか。
アメリカに話を絞る前に、まず世界的な産休の歴史に触れる。女性の労働力が評価され、出産の問題に焦点が当たるようになったのは第一次世界大戦からだ。戦場に駆り出された男性の代わりに、女性は工場で武器・弾薬を作り、野戦病院で看護に務めた。欧州では授乳の場所や時間を設定するなど、女性を動員する仕組みが導入された。だが1918年に大戦が終わると流れが変わる。帰還兵が仕事に戻り、女性の労働参加は歓迎されなくなった。1919年、国際連盟の姉妹機関として創設された国際労働機関。同年10月の第1回会議は女性の議決権を認めなかった。だがいったん自分たちの労働力や権利を意識した女性たちは、それに対し敢然と立ち上がった。アメリカの女性労働組合や活動家が世界の女性に呼びかけ、働く女性のための国際会議をワシントンで開催した。日本からは渋沢栄一の姪で、スタンフォード・シカゴ大学で学び社会学修士の資格を持つ田中孝子が、4カ月の身重の体で、はるばる日本から参加した。最初は渋っていた国際労働機関だったが、こうした女性たちの声に押され、「産前産後に於ける婦人使用に関する条約」を結ぶ。ここで初めて産前産後合わせて12週間の有給産休の考え方が導入されるのである。
産休の仕組みは第二次世界大戦後、欧州・中南米・アジアで導入されていく。特に自国が戦場となり、経済的に疲弊すると同時に、男性の多くが戦争で命を落とした欧州各国。労働力として、人口減を補う出産の担い手として、女性は重要になった。こうした経済的背景で、出産や育児を促進しつつ女性を労働参加させるための仕組みが発達していった。一方、アメリカは経済も労働人口も打撃が少なかった。戦後、帰還兵に仕事をあてがうために、女性は仕事に就かず、家庭で出産育児にいそしむことが奨励された。
その後、アメリカの女性は男性と伍して社会進出を進めていくわけだが、そこでも産休の議論が進まなかった理由は幾つか考えられる。まず、産休は女性の権利ではなく、ぜいたくや特権と見なす発想が根深く定着していた。個人を大事にし、自らを恃む傾向の強いアメリカで、個人への課税を増やし政府が社会福祉を行うことへの抵抗感は強い。それは社会主義をも想起させ、冷戦時代の対ソ緊張感が、抵抗感を増幅させてきた。また、実態とは異なるが、社会福祉の受益者が黒人などの有色人種に集中しているという思い込みが、産休制度反対の声を生んでいるという意見もある。隣国と地続き1,951マイルの国境を持ち、合法非合法で移民が流入してくる。人口減少・少子化対策で出産支援という感覚も持ちにくい。