

企画展
【現在、展示替え期間のため休館中です】
1月25日より3月16日まで
休館しております。
次回は以下の日程にて
企画展を開催予定です。
「マックス・トゥーレ:知られざるポスト印象派の画家」
2026年3月17日~5月23日
過去の企画展

初期写真資料でひも解く 着こなしの変遷―幕末・明治の女性の和装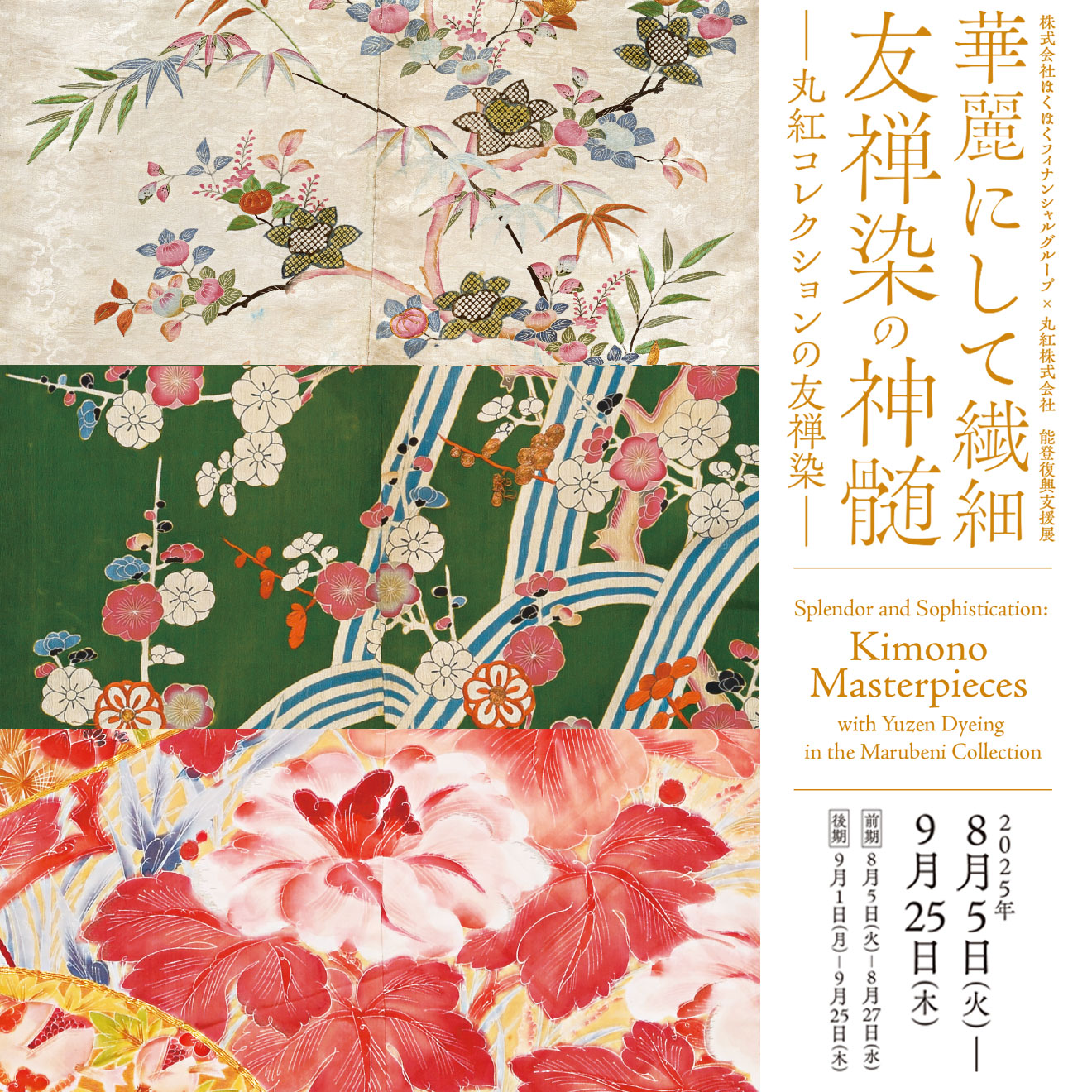
華麗にして繊細 友禅染の神髄 ~丸紅コレクションの友禅染~
『ボッティチェリ 美しきシモネッタ』特別公開展
八幡垣睦子—古裂のメタモルフォーゼ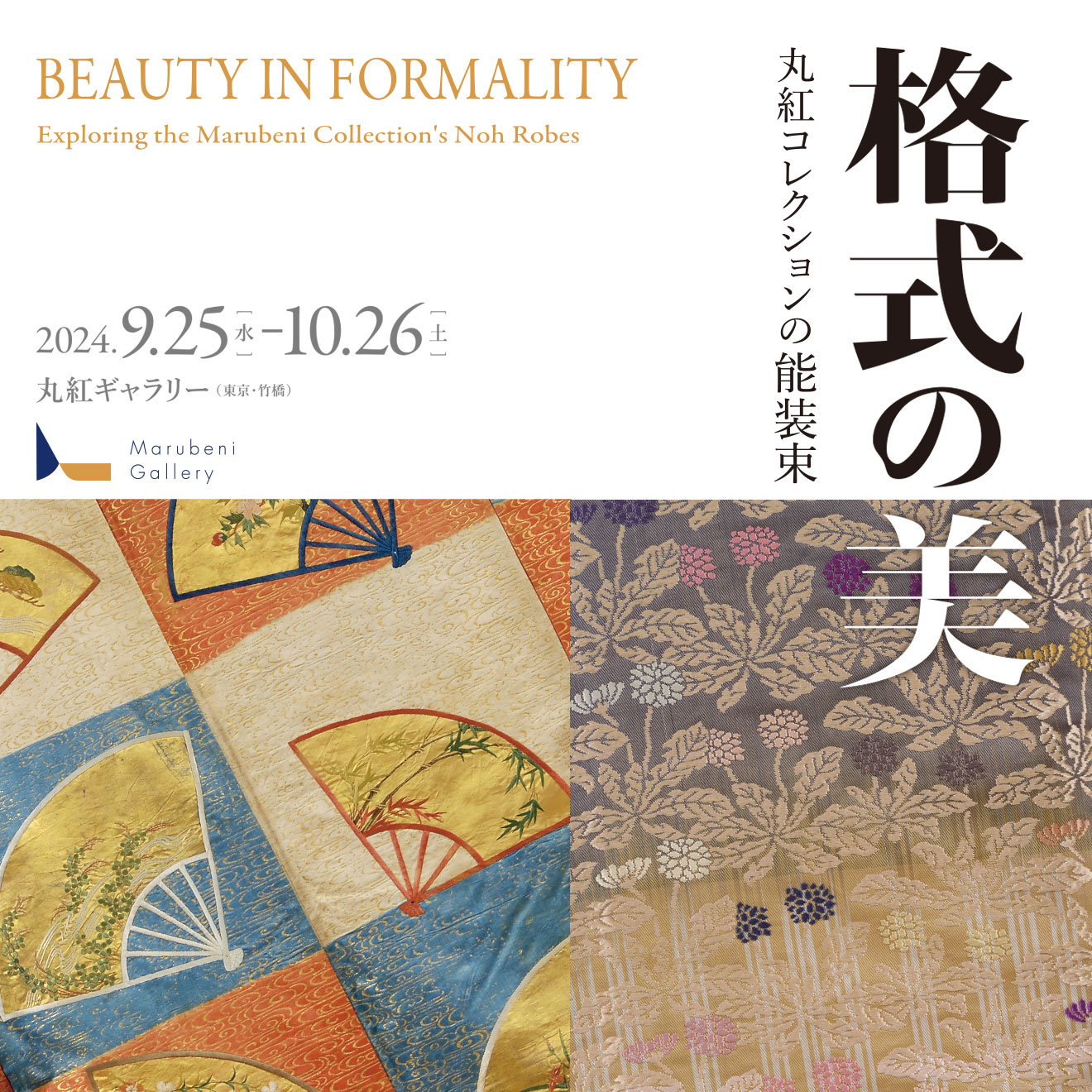
格式の美-丸紅コレクションの能装束-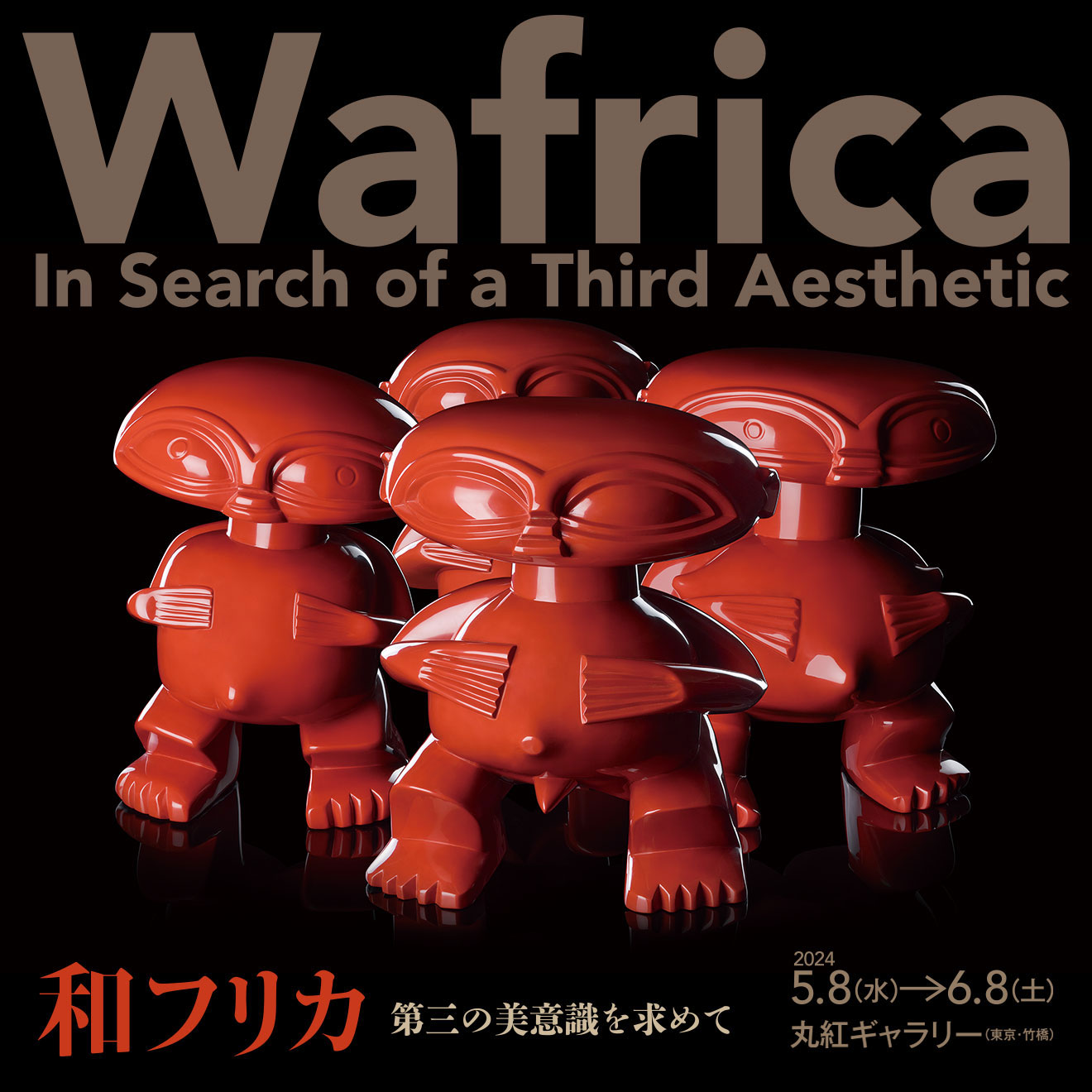
和フリカ―第三の美意識を求めて―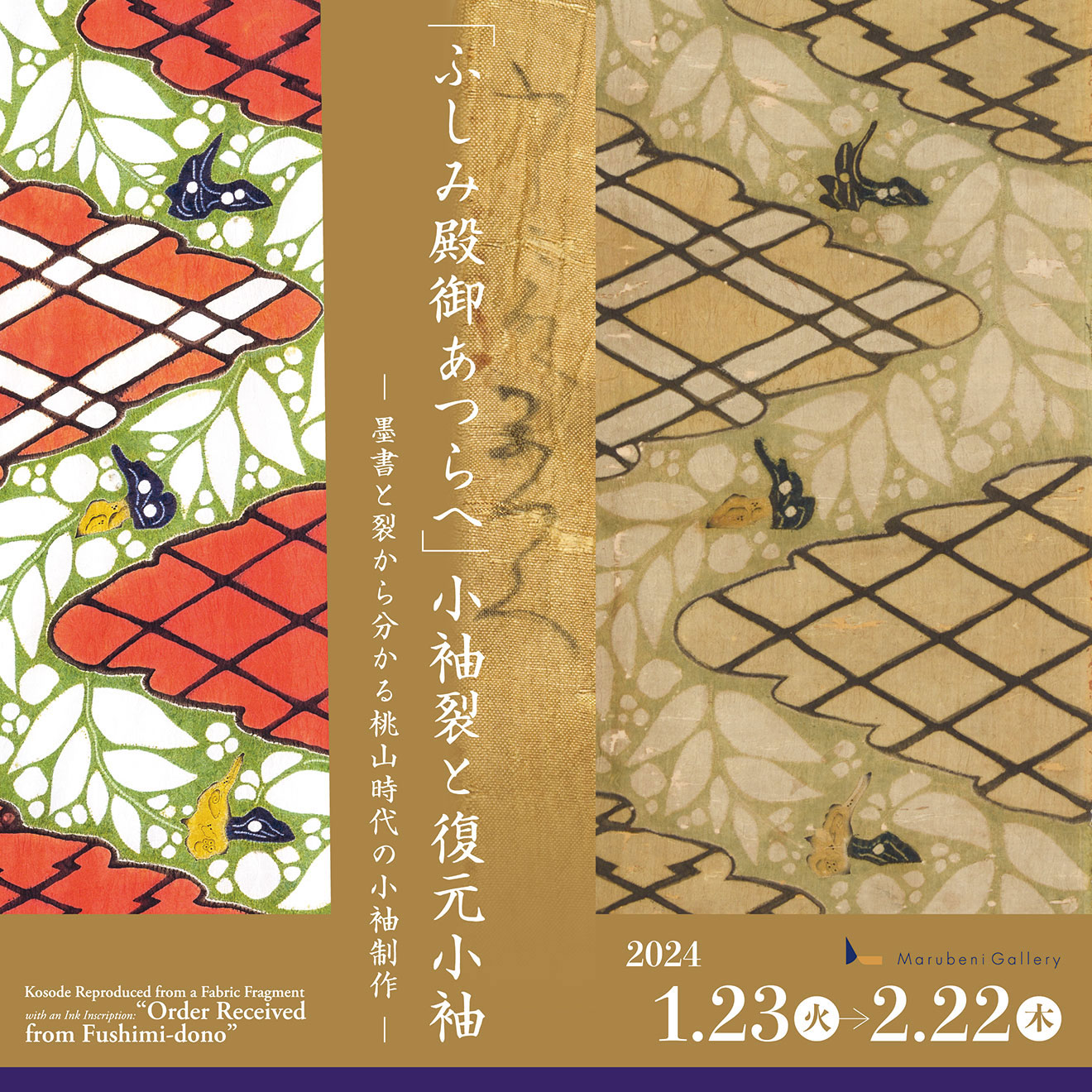
「ふしみ殿御あつらへ」小袖裂と復元小袖
-墨書と裂から分かる桃山時代の小袖制作-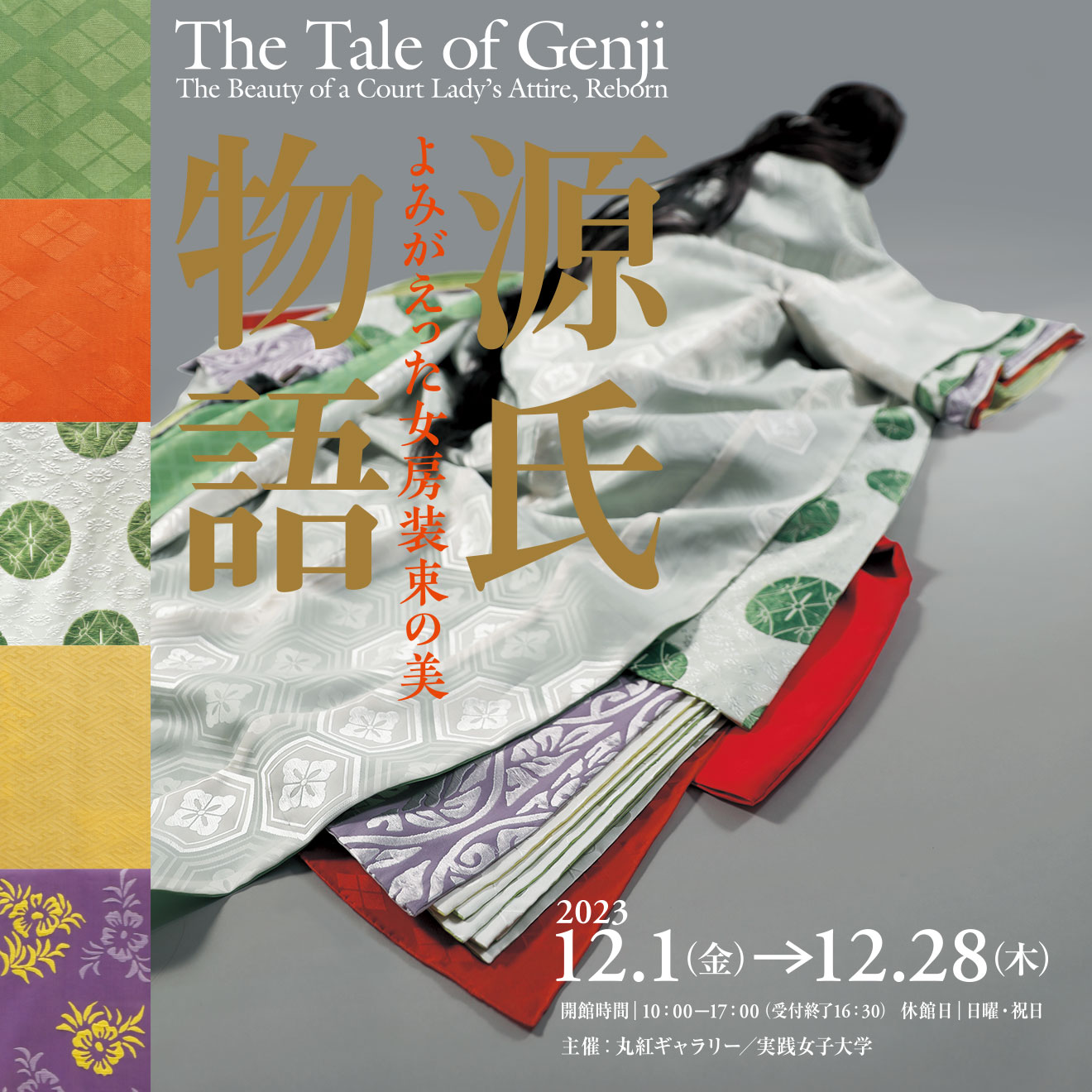
源氏物語 よみがえった女房装束の美
濱野年宏 伝統と現代のハーモニー 聖徳太子絵伝四季図大屏風(中宮寺蔵)と新作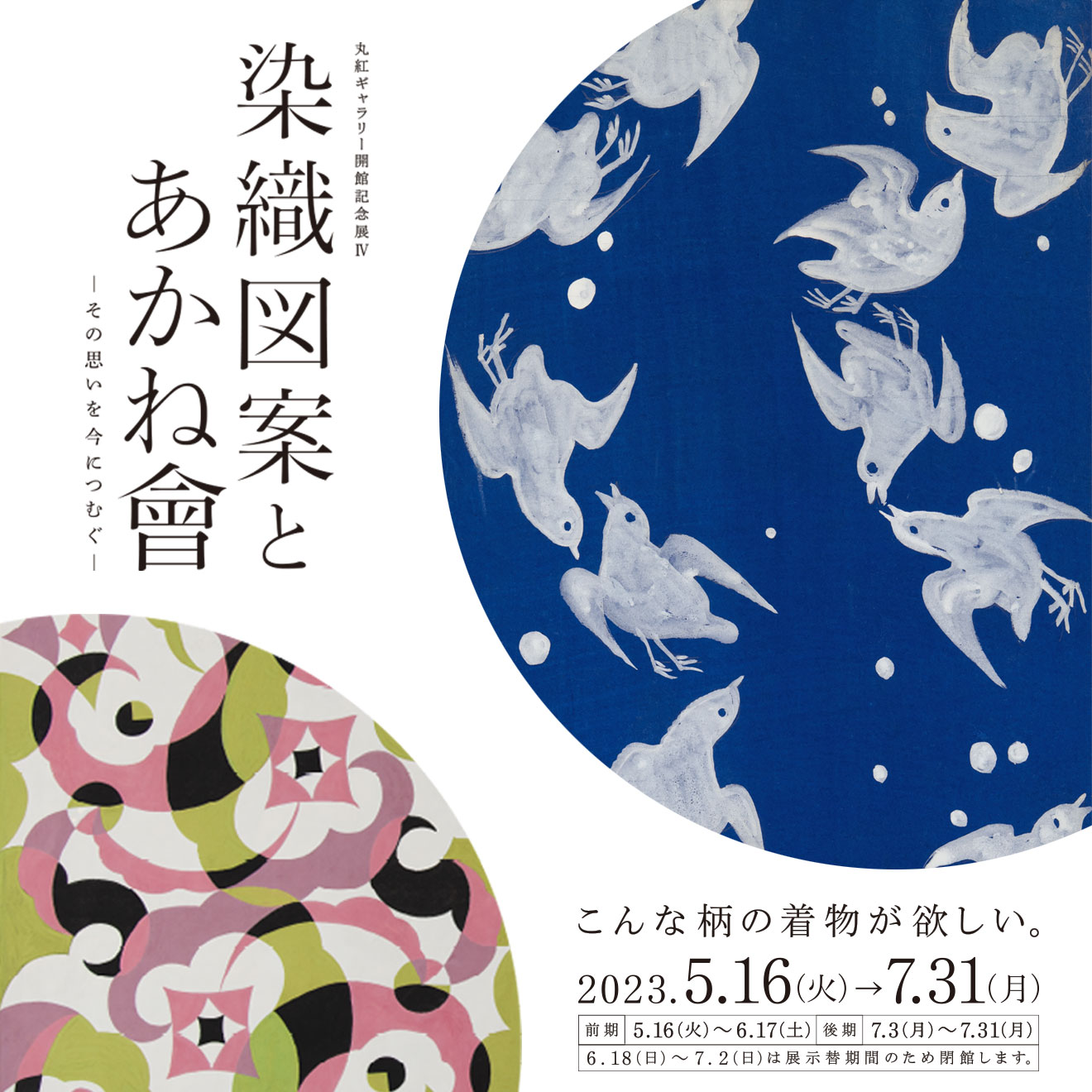
丸紅ギャラリー開館記念展Ⅳ
染織図案とあかね會―その思いを今につむぐ―
丸紅ギャラリー開館記念展III
「ボッティチェリ特別展 美しきシモネッタ」
丸紅ギャラリー開館記念展II
「美」の追求と継承-丸紅コレクションのきもの-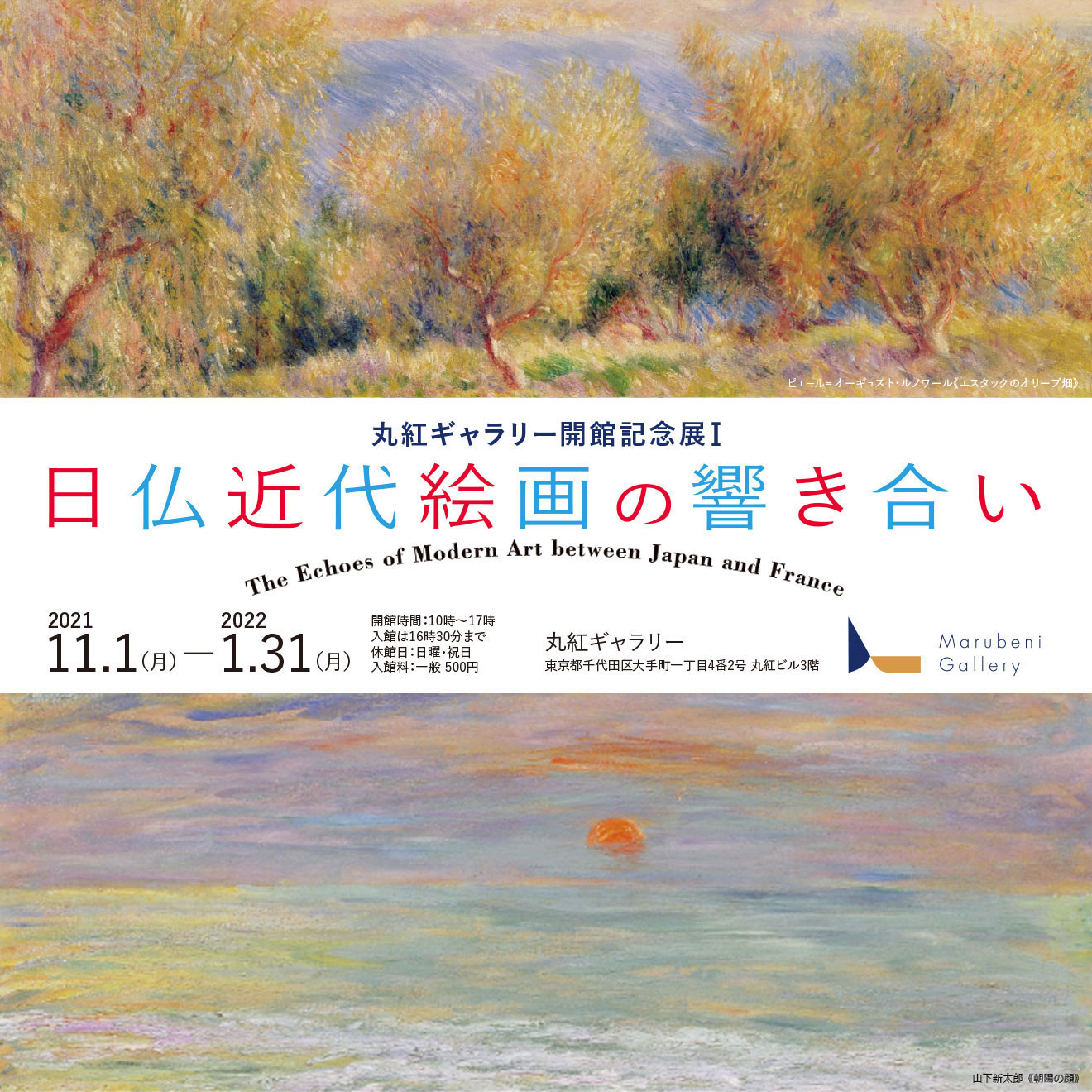
丸紅ギャラリー開館記念展Ⅰ
「日仏近代絵画の響き合い」



