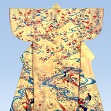丸紅が設立50周年記念事業の一環として、約3年半の歳月をかけ取り組んできた「伝・淀君の小袖」復元プロジェクトが完成しました。
これは、豊臣秀吉の側室“淀君”の時代(1567~1615)、つまり安土・桃山時代の衣装を現代によみがえらせようという壮大な取り組みです。
【養蚕から手織りまで】
それは、丸紅所蔵の時代衣装「辻が花染小袖の一片」から端を発したプロジェクトでした。左上方の縫い込み部分に「ふしみ殿御あつらへ」と読める墨書きがあり、豊臣秀吉の側室、淀君着用の小袖の一部と推測されているこの一片から、壮大な構想が静かに始まりました。そして、養蚕から糸作り、織布、絞り、染め、仕上げまで、400年もの昔をできる限り忠実に復元しようというこの構想を現実のものにするため、多くの専門家の方々の知識と技術が結集されたのが「伝・淀君の小袖」復元プロジェクトです。
当初、プロジェクト全体をご指導くださったのが、東京国立博物館名誉会員で文化財保護の権威である北村哲郎先生。しかし、途中で先生が亡くなられ、京都国立博物館の河上繁樹先生にあとを託すことになりました。養蚕から手織りまでは、北村先生の推薦により、つむぎ作りの権威である(財)萬世協会の山崎隆・京ご夫妻に一任されました。
養蚕は、97年5月より始まりました。小袖の現物に最も近い、極細で柔らかく強い糸を取るため、日本古来の蚕の原種のひとつである“小石丸”の、元気で健康な春蚕(はるご)のみを使用。さらに、京都工芸繊維大学名誉教授の布目順郎博士のアドバイスにより、繭の中のさなぎ処理は、中国の古い文献に登場する塩蔵(塩づけ)という手法で行いました [1](写真番号と符合、以下同様)。この手法は、通常の熱風で処理する乾繭(かんけん)と違って、繭を傷付けず、糸が取り出しやすく、さなぎのにおいもなくなります。
その後、繭を取り出し、水を張った特製の鍋に入れて炊きながら、1本ずつ手で繊維を引き出す「手繰り」 [2]、さらに良質の谷水にわらの灰を入れ、その灰汁(あく)で糸を炊く「灰汁練り」へと工程は進みます [3]。
実際に手掛けたのは、奥様の山崎京さん。糸づくりから手織りまでの手作業を、ほとんど1人で完成させました。織り作業をするためには、まず機ごしらえを行います。最初に縦糸にするため整経し、糸を15メートルほど千切に巻き、それを機に載せて糸を引き出して綜絖(そうこう)、竹筬(たけおさ)に通し、織り手の手元にある前棒につなぐのが機ごしらえですが、全部で1、560本もの糸を1本1本作業していく大変な作業です。また筬には、現代では通常、金筬を使いますが、復元のための極細糸に対応するため、特注の竹筬を使用。この筬は、10センチに400本近い糸を通す、非常に細い目のものです。この機ごしらえができて初めて、京さんは「これで反物ができる」と確信し、バンザイをしたくなったほどだそうです。さらに織りの際には、復元のため京さんが独自に工夫したリズムと力加減で丁寧に作業 [4]。こうした手作業の末、98年3月初旬に、美しく気品のある光沢、程よい張りと柔らかさの白生地が誕生しました。
【染め工程】
白生地完成から約1年がたったころ、プロジェクトは「辻が花染め」と呼ばれる絞り染めの工程を迎えました。「辻が花染め」は、ち密に縫い絞る技法と、墨で縁取りして金銀箔を張り付ける技法を融合したもので、安土桃山から江戸初期に頂点を極めた方法。その完成品は、華麗なる芸術作品と評されるほどです。
この絞り染めに入る前工程として、白生地の凸凹や不ぞろい部分に蒸気をあててそろえる「湯のし」をし、白生地を裁断し軽く仮縫いして「下絵羽」にします。続いて、あらかじめ「下絵羽」に絵柄を筆で入れる「下絵」、さらに下絵に沿って糸で縫う「糸入れ」の工程へ。これらの工程、そして絞りまでは、すべて京都のマツヰ染繍、松井社長の下で行われました。
そして、いよいよ絞り染めです。絞りは、染めない部分にビニールをかぶせ麻糸できつく縛る作業で、形状から“帽子”と呼ばれます [5]。今回は、糸入れから半年近くを要する手間と時間のかかる作業となり、いかに絵柄が細かく微妙かがうかがえます。 染めは、群馬県の重要無形文化財で草木染めの第一人者である草木染め研究所所長、山崎青樹氏に依頼。現存する小袖の現物から判断し、染めは3回の作業を重ねることになりました。1色目は緑。また、約400年前の現物は退色しているため、当時の発色を推測しながら山崎氏の豊富な経験による勘を頼りに色合いを決定することになります。
結局、氏の判断により、深く渋味のある微妙な緑は、藍染めの青と奈良時代から伝わる“刈安”という草を使用した黄を重ねてつくられることとなり、藍色から染めることに決定 [6]。染め上がりは、山崎氏にも満足のいくものであったそうです [7]。
2色目の赤は、厳密には「紅(くれない)」という紅花で染めた色です。染料は、山形県産の花餅を使用。花餅は、黄の成分を抜き、うすでついた後、一晩おいて陰干しして作ります [8]。炭酸カルシウム入りのアルカリ水に、この花餅を2~3時間漬け、絞って紅を抽出し、染めていきます。紅花は熱に弱く、温度に気を使いながら作業が進められ、紫外線で変色しやすいため、染色後は室内で乾燥します [9]。
赤の次、3色目の染めは黒です。厳密には檳榔子黒(びんろうじぐろ)と呼ばれる焦げ茶に近い色だそう。この染めは、室町末期よりの手法にのっとり、5種類の植物を使用 [10]。この5種類は、それぞれ微妙に違う色あいが、深みのある黒を出すことを可能とするそうです。せんじてろ過した一番液と、さらに水を加えてせんじてろ過した二番液を混ぜた染液に浸し、鉄媒染などの作業を施した後、さらに三番液を加えた染液に浸す、など工程を重ねます。
こうして染色までを終えた生地は、その都度乾ききらないうちから絞り糸をほどいていきます。この作業は、ほどくだけで何日も要するほど細かい作業です。3色目までを終えた、この段階で全体指導の河上先生にチェックをいただき、次の部分染め工程に進みます [11]。
【部分染め工程】
3回の絞り染めを終え、部分染め工程の最初は、黄色の染めです。染料には「梔子(くちなし)の実」を細かく刻み、煎じてろ過した染液を使用し、浸け染めをします [12]。この工程では、熱に弱い赤のため「温染(おんせん)」にし、また日光堅牢性に弱い「梔子の実」の黄のために陰干しする、という作業を数回繰り返します。
最後は、1色目と同じ藍色の部分染めです。場所も1色目同様、藍瓶のある群馬県高崎市の染料植物園で行われました。瓶に5分浸し、染料が行き渡るよう、しかも帽子がほどけないように丁寧に手で揉みます。その後引き上げ、すぐに水洗い。この作業を5回繰り返し、ようやく満足のいく藍色に染め上がりました [13]。
こうして染めの全工程を終了し、生地は再び京都へ。下絵を担当されたマツヰ染繍、松井青々氏に渡り、筆による彩色と補正が行われました。所々に残された白地の部分に、花びらの模様が描かれた後、補正に移ります [14]。絞り染めでは、隣り合った色と色の間に必ず多少の白い隙間ができます。その隙間を筆によって埋めていくのが補正です。この工程は、初期の辻が花染めにはあまりなく、絞り染め本来のぼんやりした輪郭よりも、くっきりした輪郭と豪華さが好まれる桃山時代に入ってから生まれたものだそうです。この工程で、紋様の彩色はすべて完了し、仕立てへと進んでいきます [15]。
【仕立てから完成まで】
仕立ての舞台は東京。「日本のきものを守る会」主宰であり、村林流和裁学苑苑長でもある村林益子先生にお願いしました。村林先生は、テレビ・婦人雑誌などを通じて、仕立ての技法のみでなく、身に着ける方への心遣い、反物に対する思いやりなども説く、仕立ての第一人者です。小袖の仕立ての際も、実際に淀君が袖を通すことは決してないにもかかわらず、身に着ける方への並々ならぬ思いやりと、生地を大切に扱われる心構えとが印象的でした。
作業は、まずヘラ付けから始められました。隣り合う生地の模様のつながりを合わせながら、コテであらかじめ折り目をつけます。そして縫いの作業に入ります。縫いは、模様に合わせてその都度糸の色を変える、というきめ細かいもの。表からは見えない、こうしたところにも、先生の奥ゆかしい心遣いが感じられます。また、絞りの加減で生地の模様が合いにくい部分は、縫いつつ表と裏から何度も確認を繰り返します [16]。出来上がった表身ごろと裏身ごろを合わせる段階で、厚味を出し保温性を高めるために、薄く伸ばした真綿を中に敷きます [17]。そして、ようやく完成へ [18]。
こうして皆さんのご協力の下、約3年半の歳月をかけて出来上がった小袖は、図柄構成の大胆さ、色使いの鮮やかさが印象的な素晴らしい作品となりました。 このみやびやかな小袖を、当時の華であった淀の方が召されたかと思うと、感慨深いものがあります。 復元された小袖は、今月から東京・大阪の高島屋で開催される、設立50周年記念の丸紅アート・着物コレクション展でお披露目されます。ぜひ皆さんお誘い合わせて、素晴らしい、いにしえの芸術ともいえる作品をご覧になってください。